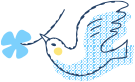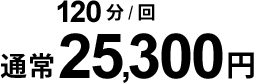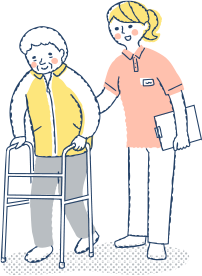脳梗塞のリハビリは
ハート脳梗塞リハビリ・ラボ
- 鍼灸治療実績
75年以上 - マンツーマン
リハビリ実施 - 東海地区で唯一
川平法を提供

脳梗塞のリハビリで
大切な3つのこと
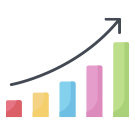

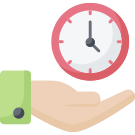
タイミング
脳梗塞による後遺症改善のリハビリでは以下の3点が大切です。
リハビリの量
退院後の保険を利用したリハビリの量は入院時と比べて1割程度となるため、リハビリ時間を確保できる施設でのリハビリが重要です。
リハビリの質
リハビリは「誰と行うか」で大きく効果が変わってきます。当施設の療法士はリハビリ専門病院で勤務経験のある者のみで運営をしています。常に「回復」のために必要なリハビリを実施することを心がけてサポートさせていただきます。
リハビリのタイミング
発症から6ヶ月以内は脳の回復にとって重要な時期と言われており、その期間のリハビリ時間が短いと回復の進みが遅くなってしまいます。そのため、可能な限り早い時期から専門的なリハビリを実施することが重要です
当施設で行う脳梗塞リハビリの特徴
脳出血の後遺症に対してハート脳梗塞リハビリ・ラボでは、リハビリと鍼治療の提供を行なっております。
後遺症により使わなくなった麻痺側の手足の機能は日に日に低下しています。
そこで、当施設ではまだ目覚めていない神経に対して繰り返し刺激を与えるリハビリ『川平法』と、適切な感覚を入力するリハビリ『ボバース法』を用いることで麻痺した手足の機能の回復を目指します。
また、ほとんどのリハビリ施設では実施していない「鍼治療」を取り入れているのも当施設ならではの特徴です。
『鍼治療』はWHOでも脳梗塞の後遺症改善に推奨されている治療法。
その中でも本場中国で行われている脳梗塞の後遺症改善に効果的な「醒脳開竅法(せいのうかいきょうほう)」を取り入れ、麻痺の回復促進を図ります。
- 麻痺の回復に特化した鍼治療
- 東海地区唯一の川平法とボバース法を掛け合わせたリハビリ
- 機能回復に特化した鍼×リハビリ
脳梗塞リハビリの治療内容

効果が期待できる主な症状
- 痛み
- 痺れ
- 筋緊張
- 関節可動域制限
- 便秘
- 頻尿
- めまい
- 高血圧
脳梗塞の鍼施術で世界的に権威がある天津中医学院附属病院と永く提携し、鍼施術を極めた「醒脳開竅法」施術を中心に、全身の気の回復を併せて提供していきます。

効果が期待できる主な症状
- 手足の麻痺
- 手足の感覚障害
- 痺れ
- 筋肉、関節の痛み
- バランス障害 など
今までの理学療法に加え、パワーリフティング等の筋力強化を併せることで機能回復が更に見込まれますので、筋力の強化を加えた理学療法を提供していきます。
脳梗塞とは
脳梗塞とは”梗塞”という「ものが詰まり流れが通じなくなる」という言葉通り、脳の血管が詰まることで脳の障害が発生してしまう病気のことです。(※1)
脳梗塞は、1951年から約30年に渡って、死亡の原因の第1位でした。現在では、その後の急性期治療の進歩により、がん、心疾患、老衰に次ぐ第4位となっていますが、脳血管障害の患者さんは現在約110万人となっており日本人の100人に1人が発病しています。(※2)
脳は人間の身体の中でも重要な器官です。多くの酸素と栄養を必要とし、動脈を流れる血液によって脳へと運ばれていきます。
ですが脳梗塞が起こると酸素や栄養が突然停止してしまいます。
そのため脳は大きなダメージを受けてしまい、重大な後遺症が残ってしまったり、最悪の場合命を落とす可能性もあるのです。(※3)
※1 出典:国立循環器病研究センター「脳卒中 1脳梗塞」
※2 出典:厚生労働省「脳卒中に関連する留意事項」
脳梗塞の原因
主な症状に「脳血栓症」と「脳塞栓症」の2つがあります。(※1)
脳血栓症
脳の動脈など太い血管にドロドロのコレステロールの固まりができてしまうと、そこへ血小板が集まってきます。
すると動脈が塞がれ血栓ができてしまい血管が詰まることによって引き起こります。
血栓ができる要因として考えられるのは、動脈硬化などによる血管壁の変化や、血液のうっ滞や濃縮などによる血流の変化、抗リン脂質抗体症候群などによる血液凝固能(血液が固まる機能)異常などがあります。
また、高血圧、高脂血症、糖尿病など生活習慣病が主因となります。
脳塞栓症(心原性脳塞栓症)
脳の血管は太い血管からいくつもの細い血管へ枝分かれしています。
その枝分かれした細い血管が詰まってしまうことにより発症します。
塞栓の最大の原因としては心臓弁膜症や不整脈である心房細動などにより心臓内にできた血液のかたまりにより起きると考えられています。
※1 出典:日本生活習慣予防協会「脳梗塞」
脳梗塞の種類(※1,2)
ラクナ梗塞(脳血栓症の一種)
「ラクナ」とはラテン語で「小さなくぼみ」という意味を持っています。
脳の中の穿通枝(せんつうし)という細い血管が詰まって起こる症状です。
高血圧などが要因となり、細い血管が詰まるものをラクナ梗塞といいます。
ダメージを受ける部分が小さいので症状が現れ辛く、無症候性脳梗塞とも呼ばれています。
症状が出ないと言っても安心できません。
放っておくと本格的な脳梗塞や脳出血を発症したり、認知症になるリスクも高まります。
アテローム血栓性脳梗塞(脳血栓症の一種)
脳の太い動脈が「アテローム」という「粉瘤」(ふんりゅう)によって狭くなることによって発症します。
太い動脈が閉塞されるので重症化するケースも少なくありません。
動脈硬化が症状のベースにあるため高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病が発症を引き起こす主な要因となってきます。
心原性脳塞栓症(脳塞栓症の一種)
心臓内でできた血栓が血流によって脳に運ばれてしまい、脳内の太い血管や複数の血管を閉塞させてしまうことによって発症します。
他のタイプの脳梗塞と比較して前触れなく突然発症します。
発症直後の神経症状の完成や失語、失行、失認などいわゆる高次脳機能障害を伴うことが多く、重症になりやすいという特徴があります。
脳梗塞の後遺症
発症後は身体の司令塔である脳に大きなダメージが残ってしまいます。
脳の細胞がダメージを負うと体の麻痺や感覚の障がい、さらには脳への障がいが残る可能性も高いのです。
症状によっては日常生活に影響が出てしまうこともあるので症状だけでなく後遺症まで理解しておくことが大切です。(※1)
運動麻痺
手足の細かい動きが難しいなど軽度のものから、口や舌の動きがスムーズに行えず、食事が詰まりやすくなる、身体のバランスが取りづらい、思うように動かなくなるなど不具合が生じます。
主に体の左右どちらかに起こることから「片麻痺」とも呼ばれています。
感覚障害
麻痺が起きた側の身体には、触れた時の感覚が分かりづらくなり、温かさや冷たさ、痛覚や触れた感覚が鈍くなる、逆に強く痛みを感じてしまうなどのケースも見受けられます。
視覚障害
視野が狭くなった、物が二重に見えるという「複視」や視野の半分が見えなくなってしまう「半盲」などがあげられます。
発症後長期間にわたって症状が残る場合もあります。
高次機能障害
呂律の回りにくさで思った通り話せなくなってしまう「構音障害」、脳の学習部分に損傷が起こって言葉を理解することが難しくなる、読み書きができなくなってしまう「失語症」。
さらには、視覚には問題がなくても物が認識できなくなる「失認」や普段使用している物の使いかたや衣服の着方がわからなくなる「失行」などの症状も起こることがあります。現れる症状は様々です。
リハビリの必要性
症状に対して社会復帰のために行う訓練を総称し、「リハビリテーション」といいます。ラテン語で「re(再び)habiris(適した)」という語源から成り、発症以前と変わらない水準の生活を目指していきます。神経機能の改善のメカニズムはまだ明かされていないことも多いです。ですが、放っておくと筋力は衰える一方なので、それを食い止めるという意味でも早期に実施することは改善に向かうための第一歩と言えます。
運動機能の改善だけでなく、一人ひとりの障害・程度に応じたリハビリを行い、ご利用者様が元々行っていた日常生活にスムーズに戻ることは心理的・社会的な改善にもつながります。それこそがリハビリの重要性といっても過言ではありません。
当施設の利用について

- オーダーメイドのリハビリを受けたい方
- オーダーメイドのリハビリを受けたい方
- 専門家の意見が聞きたい方
ご利用までの流れ
STEP2

初回お試しコースを体験
施術に加えカウンセリングも1時間行います。
症状の原因を洗い出し、わかりやすくご説明いたします。
ご利用当日の流れ
施術前カウンセリング
ご病気になられてからの経緯をお聞きします。今お困りの症状を東洋医学的、西洋医学的両方の視点で判断します。そして、生活上不便なこと、これから叶えたいことなどについてしっかりとお伺いします。

施術
鍼灸、リハビリ、トレーニングの流れで当施設の施術を体験していただきます。

結果のご説明
身体を動かしていただき、痛みの軽減や可動範囲の広がりを確認、ご説明いたします。
また、ご自身でできるお身体のケアについて説明していきます。

動画によるご説明
Questionよくいただくご質問
病院から退院した後すぐの方から、発症後数年経過された方まで通われています。
また、脳梗塞、脳出血だけでなく、パーキンソン病、脊髄損傷、脊柱管狭窄症等の疾患をお持ちの方から、介護度は要介護5まで、リハビリが必要な方はどなたでも利用することが可能です。
鍼治療と理学療法を合わせた、マンツーマンの完全オーダーメイドプログラムとなります。
利用者様の夢や目標を大事にし、それに向かってリハビリを組み立てていきます。
具体的には、「装具を外して歩きたい」という目標がある方は、装具を外して歩くための練習をします。
「箸を使って物を食べたい」という目標がある方は、箸を使えるようになるための練習をします。
時間も合計120分と充実した内容になっています。
ご利用希望の方は、初回お試しコースから受けていただいています。
一度どのようなリハビリ内容かを体験した上で、これなら効果を実感できそうだと思った方のみ、本利用に進んでいただいています。
まずはお気軽に初回お試しコースをご利用ください。
可能です。
デイサービスやデイケアと併用して利用されている方もいます。
従来の介護サービスを利用しながら、リハビリを行うことで、更なる効果も期待できます。
ございません。
提携駐車場がありませんので、近くのコインパーキングに止めていただくことになります。
目安は打ち止め料金で平日2,200円~、土祝1,000円~になります。