皆様は脳梗塞のリハビリ方法についてご存知ですか?
初めて入院された方やそのご家族様はこれからどのようなリハビリが行われるのか不安かと思います。
数あるリハビリの中で代表的なのもや、リハビリ・ラボでも行うことが多いものを厳選して解説をしています。
病院入院中や退院後のリハビリの選択に役立てて頂けると良いかと思います。
【脳梗塞はなぜリハビリが必要なのか】
脳梗塞は脳の血管が詰まってしまう病気です。

血管が詰まることにより、脳細胞へ血液が送ることができなくなってしまい、血流が行き届かなくなった脳細胞は死んでしまったり働きが弱くなってしまいます。
その結果、様々な後遺症が出現します。代表的な後遺症は、「運動麻痺」「感覚障害」「嚥下障害」などがあげられます。
ほかの病気は病院を退院すると完治している状態ですが、脳梗塞の後遺症は病院を退院しても残ります。現代の医療では完治が難しいと言われているのです。
しかし、厄介なのは後遺症をほったらかしにすると症状が悪化してしまうことです。
そこで、リハビリを継続的に行い、仕事や趣味、日常生活で困らないようにすることが大変重要になります。
【どのくらいの期間リハビリを行えばよいのか?】

目標の有無にかかわらず、リハビリ(トレーニング)はずっと続けることをお勧めします。
特に発症から1年以内は療法士とマンツーマンでリハビリを行うことで後遺症がより回復します。また、1年以上経過している方でも目標をお持ちの方は、療法士と専門的なリハビリを実施することで、より早く目標を達成することが可能です。
目標達成後もお身体の状態を維持するために、自主トレを続けて日課にしましょう。
【病院を退院した後のリハビリの現状】
しかし、実際には病院を退院してからの生活で、回復の実感が薄れていく方が大勢いらっしゃいます。
なぜなのでしょうか?
それはリハビリの「量」と「質」の双方に問題があります。
- 量の問題
退院後の保険のリハビリでは個別のリハビリ時間が大幅に減少してしまいます。
回復期の病院では毎日3時間=週21時間=月90時間も取り組んでいたリハビリが
退院後は月8時間となってしまいます。1割にも満たないのです。
- 質の問題
退院後のリハビリは種類によっては個別ではなく集団のリハビリになってしまいます。ゆえに○○体操のようなものになってしまい、一人ひとりに合わせた内容を実施することができません。
また、個別のリハビリができたとしても、療法士を選ぶことはできないため、担当になった療法士次第で回復曲線が大きく変わってきてしまいます。
【脳梗塞のリハビリで注意したいこと】

では、後遺症を回復するために「たくさん」運動すればよいのかというと、そういうわけではありません。
脳梗塞のリハビリで注意するポイントを3つあげます。
- とにかくたくさん動かす はNG
先ほど、回復には「量」が必要ですとお伝えしました。しかし、ただ闇雲に動かしても麻痺した手足が回復することは難しいです。
野球選手が素振りを1万回したら大活躍できるわけではないのと同じです。自分のよさをよりよくするためには、何が必要なのか?それを的確に行うことでより効果を発揮します。
- 自己流でもいいから歩く はNG
歩き方をよくするためにはたくさん歩くことが大切であると思っている方は大勢いらっしゃいます。確かに、そのような方もいらっしゃいますが、多くの方は徐々に自己流の歩き方が定着してしまいます。すると、「きれいな歩き方」「速い歩き方」から遠ざかってしまうことを多く見受けられます。一度定着してしまったものを、定着し直すことはとても時間を要します。自己流にならないように指導をしてもらうことが大切です。
- リハビリ=もみほぐし はNG
筋緊張が高い部分(こわばってしまう部分)をもみほぐすことは重要です。しかし、それで終わっていませんか?なぜ筋緊張が高くなってしまうのか、動作をどのように改善したら筋緊張が高くならなくなるのか、それを一緒に解決していくのがリハビリの本質です。
時には寝てほぐすことはありますが、これから解説する「基本的な動作」、「日常生活で使う動作」を行うことで改善への一歩となるでしょう。
【脳梗塞のリハビリとは】

脳梗塞のリハビリは大きくわけて3つあります。
- ①身体を動かす基本的な動作のリハビリ
- ②日常生活で使う応用的な動作のリハビリ
- ③嚥下機能と言葉のリハビリ
今回はそれぞれ順を追って説明していきます。
①身体を動かす基本的な動作
基本的な動作は退院後に生活するために必要な動作になります。
わかりやすい動作としては
- 起きる
- 座る
- 立つ
- 歩く
などが基本的な動作になります。

また、上記の動作を行うための関節の動き(関節可動域)を確保するのもリハビリの1つになります。
②日常生活で使う応用的な動作
退院した後にに日常生活で使用する動作になります。
具体的には
- 服を着る
- トイレで排泄をする
- 入浴する
- 食事をする
などが日常生活動作になります。
先ほどお話しした基本的な動作よりさらに細かく繊細な動きが求められることが特徴です。

③嚥下機能と言葉のリハビリ
脳梗塞になると嚥下機能(飲み込みの機能)や言葉がうまく喋れなかったり、理解ができなくなってしまうことがあります。
嚥下機能が悪くなると、むせ込みが多くなったり、食事にとろみをつけて食べることになります。
嚥下も言葉も症状に合った方法で行わなければいけないため、より専門的な知識が必要となります。

【脳梗塞のリハビリの種類】

脳梗塞の後遺症の方々の動作を改善するためのリハビリは3つの種類に分かれています。
①理学療法
基本的な動作を身につけるためのリハビリです。病院では良く「足のリハビリ」と呼ばれることもありますが、足に限らず身体全身の動作を診ていきます。可動域訓練や体力強化訓練、基本動作訓練、歩行訓練などが代表的なものになります。
その他にもロボットを使用した歩行訓練や装具を使用した装具療法も行なっています。
②作業療法
日常生活の中で使う動作を身につけるためのリハビリです。病院では「手のリハビリ」と呼ばれることもあります。日常生活では手を使う動作が多いですが、股関節や足の動作が必要な場合はそちらにも介入していきます。
③言語療法
嚥下機能の訓練や言葉のリハビリを行います。食事の際のトロミ調節は飲み込みの検査をして細かく調節をしたり、コミュニケーションを円滑に行えるように、言葉の出やすさや発音などの練習をします。呂律を改善する構音訓練や注意障害などに対する高次脳機能訓練なども行います。
【脳梗塞のリハビリ方法8選】
では、理学療法、作業療法でどのようなリハビリの方法・手技があるのか簡潔に紹介していきます。
①促通反復療法(川平法)
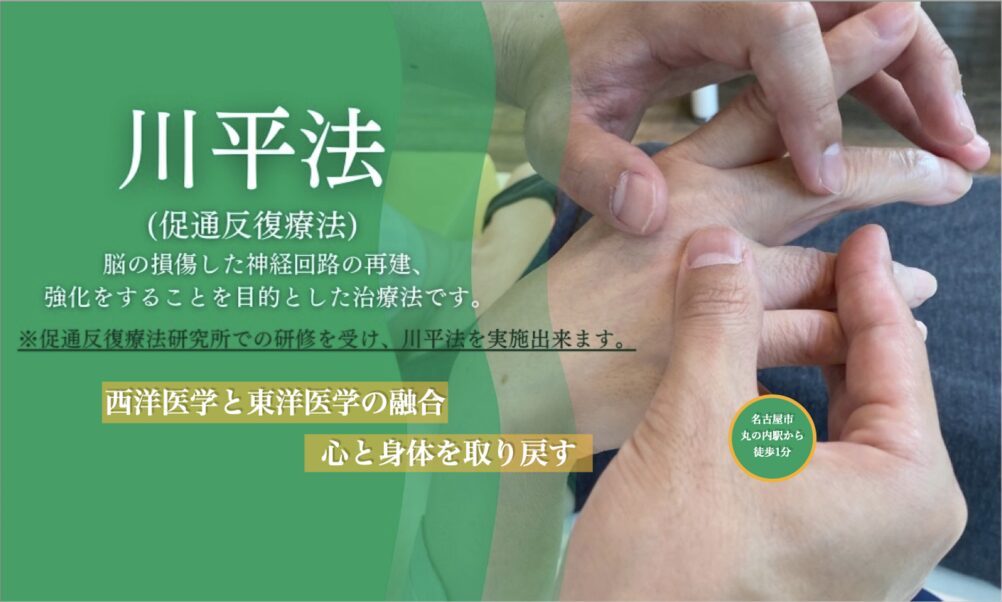
麻痺した手足を操作し、意図した動作を反復して行うことで、大脳から脊髄までの神経回路を再建・強化する方法です。
一般的には「川平法-かわひらほう」と呼ばれています。
川平法は当施設で実施している治療方法の1つで、リハビリ・ラボは公式に認定された施設になっています。
②CI療法
CI療法は麻痺していない方の手をミトンなどで覆ってしまい、麻痺している手を強制的に使用させることで、神経の回復を促進させる治療法です。
しかし、実施には多くの時間がかかることもあるため、近年では修正CI療法という簡易的に行う方法なども出てきています。
③装具療法
脳梗塞のリハビリにおける「装具療法」は主に足につける装具を意味します。
立っているときや歩いているときに膝が折れてしまったり、足首が捻じれてしまう方に対して装具を使用します。
きれいな歩きとは離れてしまうこともありますが、歩く距離・活動量が増えるため、病院ではほとんどの方が作製されます。
④ミラー療法(ミラーセラピー)
鏡を使って麻痺した方の手を動かしたと錯覚させ、痛みなく運動を行わせて学習を図る治療法です。
鏡の後ろに麻痺した手を置いて、麻痺してない方の手を鏡に映し出すことで、麻痺した手が動いたと錯覚させます。
⑤高次脳機能訓練
注意障害・記憶障害・認知障害・遂行機能障害などに対して訓練するものになります。
高次脳機能の訓練は動作を何度も反復して練習するほか、実際の生活に近い環境で練習したりと、課題によって異なります。
⑥ボバース療法(ボバース概念)
イギリスの医師が開発し、全世界で普及しているリハビリの治療方法(治療概念)のひとつです。ボバース概念は一人ひとりに合わせた治療プログラムを組み立てます。完全オーダーメイドの治療プログラムはボバース療法(概念)のみの特徴です。
⑦ロボット療法
現代は様々なロボットが普及されています。リハビリ業界でも手と足ともにロボットが普及し始めています。
ロボットは療法士の代わりの役割もしているため、自宅の自主トレとして使用されるとマンツーマンのリハビリの効果が維持しやすくなります。
⑧その他のリハビリ方法
上記の3種類以外にも様々なリハビリが近年増えてきています。
- r TMS(反復経頭蓋的磁気刺激)
- t DCS(経頭蓋直流刺激)
- t ACS(経頭蓋交流刺激)
などの直接脳を刺激する治療法が近年多く見られています。
また、再生医療も少しずつ普及してきています。培養した幹細胞の点滴をしながら同時にリハビリを行って神経の回復を図るようです。
【保険を使わないリハビリの特徴】

実は、病院を退院したあとのリハビリの提供先が増えてきていることはご存じでしょうか?今までは
・病院での外来リハビリ:週に1.2回をマンツーマンリハビリ(発症後数カ月までという制限がある)
・医療や介護機関での通所リハビリ(デイケアやデイサービス):集団リハビリor20分程度のマンツーマンリハビリ
・自宅での訪問リハビリ:週に2回をマンツーマン
の3つから、使える保険の種類や生活スタイルから選ぶことができました。
昨今では、この3つのリハビリに加えて「自費リハビリ」という選択肢があります。
自費リハビリの特徴は以下の通りです。
| 自費リハビリ(リハビリラボの場合) | 保険を使ったリハビリ | |
| リハビリ時間と頻度 | 時間:120分 頻度:週1~週5まで選択自由 | 時間:20分~40分(長くて60分) 頻度:週1~週2が多い |
| 役割と目標 | 役割:利用者の希望に応える 目標:麻痺を治す・旅行に行く など幅広い夢を叶える | 役割:現在の機能を維持 目標:道具などを工夫して行える動作を増やす |
| 手技 | 麻痺を回復するための手技を磨いてきた療法士 リハビリ病院で経験した療法士 が担当 | 療法士によるが、多くの療法士は マッサージを主としたリハビリ |
| 担当療法士 | 選べる | 選べない (実力のある療法士が担当するかは運の要素) |
決して安くない金額ではありますが、「麻痺を回復させることをあきらめない」という強い気持ちを療法士・利用者ともにもって取り組みます。
【リハビリラボはどんな内容?】
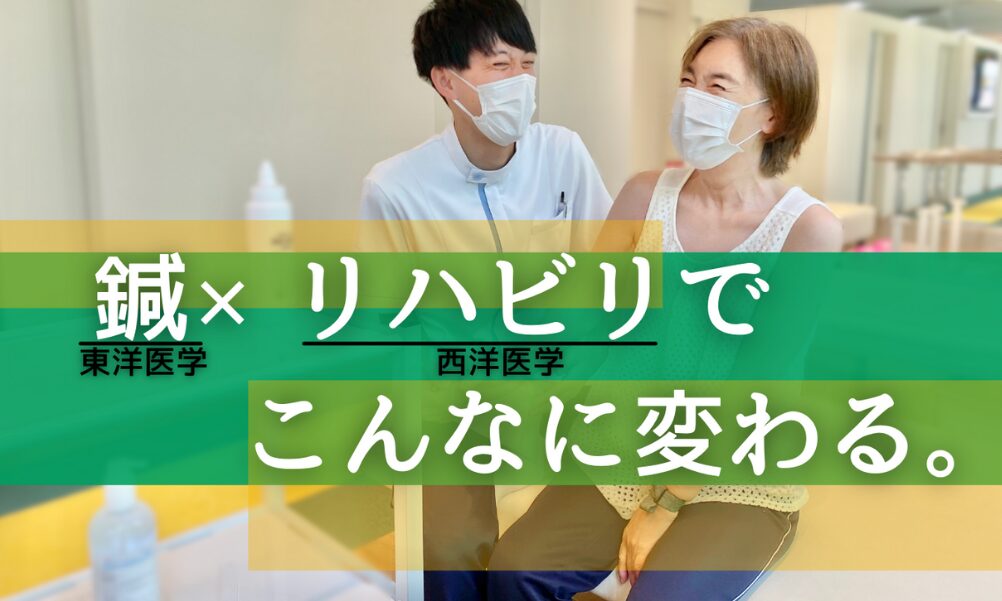
最後に、当院のリハビリの内容を説明いたします。
当院のリハビリは毎回120分間実施いたします。しかし、病院等で行ってきたリハビリとは異なり、60分間鍼療法の治療をし、そのあと60分間の運動療法を行います。
「デイサービスのリハビリがマッサージだけで終わってしまう」という声をよく聞きます。当院のリハビリはマッサージをする時間は少なく、「麻痺を回復する」ための治療を実施いたします。そのため、施術者は脳梗塞の専門的な手技を取得しています。
具体的には、前述したリハビリ方法の中の①促通反復療法(川平法)、③装具療法、⑥ボバース療法を軸に治療プログラムを構成します。
また、手の麻痺の方に対しては⑦ロボット療法の活用も致します。動作以外に希望がある場合は⑤高次脳機能訓練を中心に行う場合もございます。
当院のリハビリは他では受けることができないワンランク上の治療となっています。
【実際の利用者さまの紹介】
疾患:脳梗塞(右片麻痺)
発症:約1年前
目標:右手を使えるようになりたい、字を書いたり箸を使えたりできるようになりたい
当初、食事はスプーンで食べられておりましたが、通院して1か月後には介助箸を使って食事をとることができるようになっております。
また、3カ月経過すると指、手関節の動きがスムースとなりものをつまむことが容易になりました。
現在、無料お試し期間中ですので、「本当は諦めたくない」と少しでもお気持ちがある方は一度ご連絡ください。
相談だけでも構いません。お待ちしております。
※大好評につきご予約がお取りできない日もございます。
ご予約はお早めに!
この記事を書いた人

松浦 一将 理学療法士
JBITA公認 成人片麻痺基礎講習前講習1、2修了
大学卒業後、回復期リハビリ病院へ入職。主に脳梗塞・脳出血の患者様のリハビリを担当。同病院で訪問リハビリも経験させて頂き、より患者様の「生活」に近い場所でリハビリに携わってきました。2022年ハート脳梗塞リハビリ・ラボへ入職。「麻痺をよくしたい」という方はもちろん、前職の経験も活かし、目標に向けた最適な自主トレや運動方法のご提案、情報提供も行っています。 皆様の何気ない「笑顔」を大切に、目標を達成して共に成長できるよう全力でサポートさせて頂きます。
